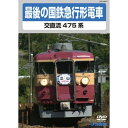いつも当ブログを御贔屓いただきまして、誠にありがとうございます。
ようやく緊急事態宣言が全国的に解除されました。
休業要請やステイホームの効果は一定程度あったと評価されるのでしょうが、このままでは閉店や倒産等が非常に心配です。
来るべき第2波への警戒をしつつ、いつもの生活に近い新しい生活形態をどうやっていくのかを毎日探り探りでやっていくしかないようです。
新しいことは古いことの中にヒントがある、「故きを温ねて新しきを知る」ということで、本日は「故き」車両のBトレインショーティーをご紹介させて頂きます。。

JR西日本 457系交直流電車 新北陸色 です。

元々は、153系を祖とする デッキ付き2扉、固定クロスシート車両、いわゆる急行型電車の系譜となります。

この系列は分類が多く、交直流電車の祖となった401系・421系と同時に開発が始まり、電動機出力や、抑速ブレーキと呼ばれる勾配対応、50Hz・60Hz・両電源対応等で形式が細かく分類されています。

そのあたりのお話は他に譲るとして、交流・直流の両区間を走破できる性能を持つため、交流区間である東北・北陸・九州と東京・大阪・名古屋を結ぶ急行電車として大変重宝されました。

しかし、時代が進むとデッキ付き2扉・固定クロスシートの急行型車両というのは接客設備としては中途半端感が出てきてしまいます。

長距離輸送はより居住性の良い特急車両へ、大都市圏での輸送は大量輸送とよりスムーズな乗降が可能な近郊型車両へと主役が移ってきます。

その頃と同時に大都市圏以外のエリアでの「特急・貨物優先」の客車輸送による普通列車に不等ダイヤを見直す動きが盛んになります。

北陸地区においては、1985年のダイヤ改正で30分間隔のパターンダイヤが導入されます。

その際に多くの電車が必要となるのですが、交直流対応車両は電装品が高価で当時の国鉄では増備が難しい状況でした。

そこで、徐々にダブつきがちとなった457系急行型電車を用いると共に、同じく余剰となっていた583系を魔改造した419系「食パン電車」を導入し、その運用に充てました。

その際に457系は短編成化され、主に3両編成で運用が行われていました。

運用当初は、赤い塗色に白帯を巻いた姿でしたが、その後、このBトレのように白い車体にブルーの帯を巻くようになりました。

当時の関西エリアでは、デッドセクションと呼ばれる交流・直流の切り替えエリアがあった滋賀県の長浜以北に生息しており、稀に米原駅にも顔を出しました。

この色の457系には個人的にも乗車経験があり、非常に思い出深い車両です。

457系の栄枯盛衰としては、「枯」や「衰」の時期にあたる塗色ではありますが、北陸エリアの鉄道輸送の近代化に大きく貢献しました。

その後北陸地域色と呼ばれる真っ青な塗色に変更し、2015年3月をもって営業運転を離脱、後進の521系にその任を譲りました。

457系の晩年期を象徴する新北陸色のBトレの姿を眺めつつ、457系の栄枯盛衰を今一度噛締めてみたいと思います。↑↑ご紹介済み車両をまとめた索引ページを設けました↑↑
ご紹介順にたどりたい方はこちらから~百々怒涛のブログ~鉄道コム

- 価格: 929 円
- 楽天で詳細を見る